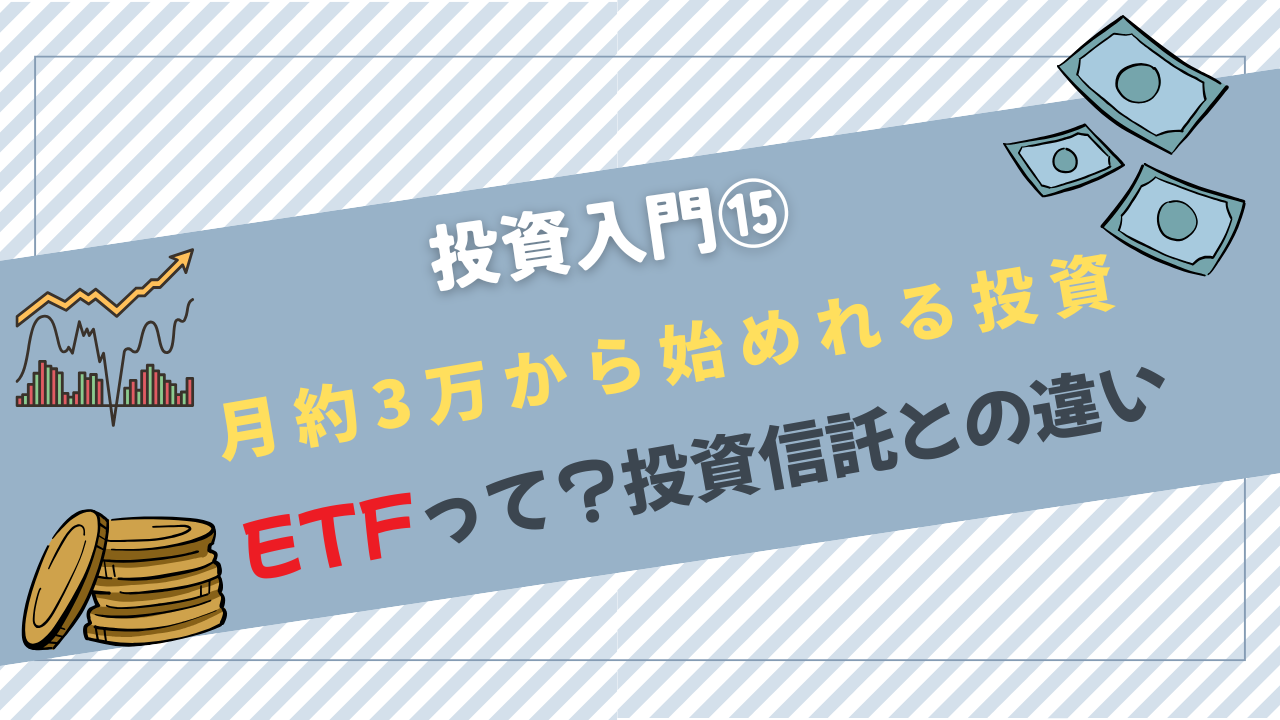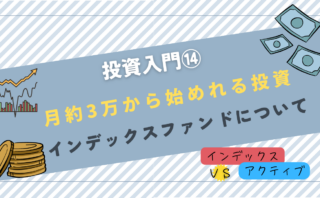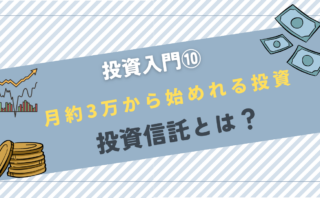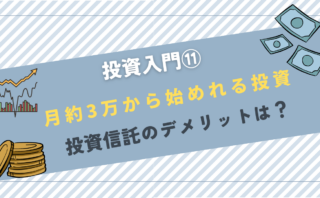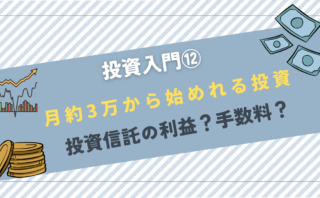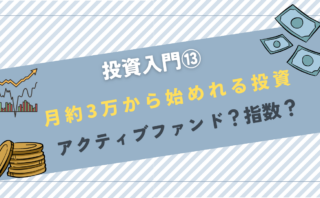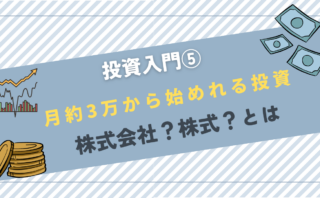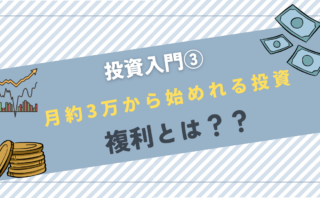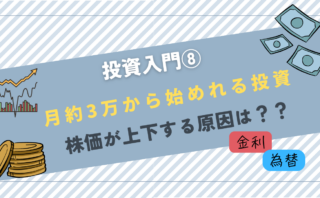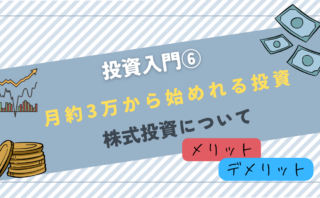こんにちは。tkgです。
前回は、
インデックスファンドについての説明から
具体的な商品を紹介した上で、
アクティブファンドとの比較を
紹介させていただきました。
今回は、
最近よく聞くETFという
商品について紹介させていただきます。
前回のおさらい
- インデックスファンドは
株価指数に連動する投資信託 - アクティブファンドに比べ、
ローリスク・ローリターン - 長期投資・初心者は
インデックスファンドがおススメ
インデックスファンドは
初心者向けでもありますが、
長期投資では安定しており、
長期的にみれば、
アクティブファンドより成績も良い事例も
紹介させていただきました。
これまで投資信託という商品の中身を
紹介してきましたが、
今回はETFという商品について紹介します。
ETFとは
ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/etf/index.html
「Exchange Traded Funds」の頭文字をとりETFと呼ばれています。
キーワードは
上場 という部分です。
ETFは上場投資信託と言われ、
投資信託の1種となります。
一番の違いは
株式と同じように証券取引所で
売買されるということ
上場してる=株式のように
リアルタイムで売買可能ということです。
ETFは、特定のインデックスに
連動する形で運用されることが多く、
低コストで分散投資が可能な点が魅力です。
取引方法
ETFは、株式と同様に証券取引所で
リアルタイムに取引が行えます。
これにより、投資家は市場の動きに応じた
タイミングで売買ができるため、
非常に柔軟な投資が可能です。
証券会社を通じて、
通常の株式同様に注文を出すことで
購入ができます。
| 証券会社に依存しない売買可能とは? (S&P500の商品例の場合) | ||
| 投資信託 | ETF | |
| 楽天・プラス・S&P500 | SBI・V・S&P500 | ・上場インデックスファンド 米国株式(S&P500) ・MAXIS米国株式 (S&P500)上場投信 等 |
| 楽天証券でしか買えない | 14社から購入可能 | 全国の証券会社で購入可能 |
特徴にもあるように、
投資信託の商品によっては
証券会社に依存することで、
好きな商品を買うためには
特定の証券会社を作らないとダメです。
一方、ETFでは、
好きな商品があればどこの証券会社経由でも
購入可能となります。
価格の決まり方
ETFの価格は、
基本的には市場の需給によって決まります。
流動性が高い(売り買いが多い)ETFであれば、
価格はその商品の基準価額に近い価格で
取引されることが一般的です。
しかし、
流動性が低い(売り買いが少ない)ETFの場合、
売買の差が
(実際の商品の価格と売り買いする価格)
広がることがあるため注意が必要です。

上がったのに
下がってるーー!!!
ってなります。
株式同様なので指数に連動しても、
人気なければ上がらないって感じです。
主に、
- ETFの運用資産が少ない
- ニッチなテーマ
- 発行元の規模が小さい
等の原因により下がる場合があります。
ただ、指数に連動しないと困りますね
(-_-;)(-_-;)(-_-;)
アービトラージという仕組みで
価格が安定します
インデックスETFは投資信託のように
個別に運用指示するような
ファンドマネージャーはいなく、
運用方針があらかじめ決まっています。
ETFは外部化されており、
そこで儲ける大口投資家(AP)いるという
イメージです。
例えば、
ある商品、
鉄鋼のETF(A)があったとします。
(そのETFは鉄鋼株30銘柄が含まれる)
| ETF名 | A |
| 構成銘柄 | 30銘柄の鉄鋼株 |
| 状況 | Aの市場価格が、 実際の30銘柄の 合計価値よりも高い A>30銘柄の鉄鋼株 |
- 1空売り
APはA>30銘柄になってるので
Aを空売り
(例えば、1000シェア空売り) - 2現物株の購入
同時にETFの中身と同じ、
鉄鋼30銘柄を買い集める
(全体で1000株分) - 3持ち込み
現物株をETF側の信託銀行に持ち込み
- 4新しいETFの受け取り
信託銀行から新しいAのシェアを発行
APに1000シェアを渡す - 5空売り決済
最初の空売りしたAを
新しく発行されたAで買い戻し
- 価格差の利益:
- 例えば、APが空売りしたAの価格が30ドルだったとします。
- その後、APが新しく受け取ったAを28ドルで買い戻した場合、
1シェアあたり2ドルの利益。 - 1000シェアの場合、
総利益は2000ドルになります。
こういったイメージで
市場指数に連動する動きがあり、
ETFの価格安定が担保される仕組みです。
具体的な商品
多くのETFは特定の指数に連動しており、
日本国内では
「日経225連動型上場投資信託」や、
「TOPIX連動型上場投資信託」が有名です。
また、海外市場にも多くのETFが存在し、
S&P500に連動するETFなども人気です。
| 順位(国内) | コード(国内) | 銘柄(国内) |
| 1 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
| 2 | 1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 |
| 3 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 4 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
| 順位(海外) | コード(海外) | 銘柄(海外) |
| 1 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF |
| 2 | SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF |
| 3 | TSLL | Direxion デイリー TSLA ブル2倍株式 |
| 4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF |
※2025年2月の売買代金
一方、
以下のような指数に連動しない
アクティブETFもあります。
ETFと投資信託の違い
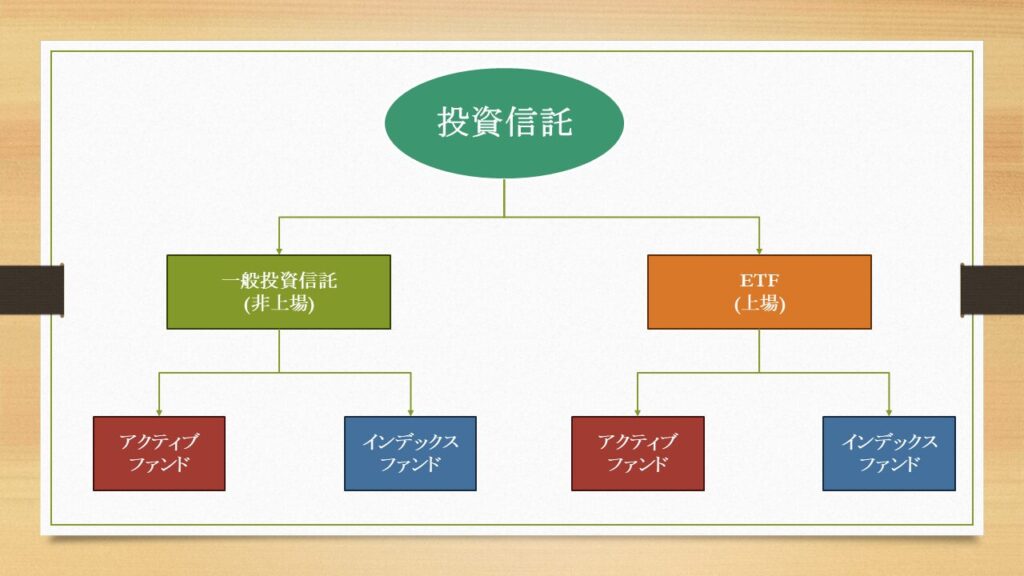
上記のように、
ETFと投資信託の大きな違いは、
「上場」・「非上場」の違いで、
以前に紹介したのは非上場のものとなります。
細部での違い以下です。
| 投資信託 | ETF | |
|---|---|---|
| 上場有無 | 非上場 | 上場 |
| 購入場所 | 証券会社 銀行・郵便 など | 証券会社 |
| リアルタイム取引 | できない | できる |
| 購入金額 | 100円~可能 (金額指定OK) | 株式同様、 単元指定 |
| 定額購入 | できる | できない (一部可) |
| NISA購入 | 可 | |
| 購入価格の決定方法 | 基準価額 | リアルタイムの市場価格 |
| 銘柄数 | 約5~6千銘柄 | 約300銘柄 (国内) |
| 分配金について | 再投資可能 | 再投資不可 |
| 信用取引 | できる | できない |
| コストについて | ||
| 信託報酬 (運用管理費用) | ETFより高め | 投資信託より低め |
| 売買手数料 | ゼロのファンドが多い | ネット証券では ゼロ~数百程度 |
| 売却手数料 | 株式同様 ゼロ~購入金額によって変化 | |
| 為替手数料 (海外ETFの場合) | 基本的に円での投資 (管理費用に含まれる場合が多い) | 外国ETFの場合は 為替手数料がかかる |
購入について
実際に購入するとなった場合、
以前、投資信託では100円からの
少額投資が可能なことは説明しましたね。
ETFでは?
こちらは基本的に株式同様、
1株などの価格から購入です。
株式は基本100株単位の制約もありますが、
ETFは各会社で最低購入数が決められてます。
| 銘柄名 | SPDR S&P500 ETF | 上場 インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100) |
| 価格 | 84,280円 | 5047円 |
| 最低購入単位 | 1株単位 | 10株単位 |
| 最低購入金額 | 84,280円~ | 50,470円~ |
上記のように、
ETFでは現在の市場価格から購入となるので、
比較的大きな金額が必要な場合があります。
一部のETFでは
少額から自動定額購入
できるものもありますが、
買えるものも銘柄が少なく、
基本的に市場価値は
1株以上からになるので、
あまり美味しいものではないですね。
分配金について
分配金の再投資有無の違いがありますが、
分配金再投資の複利の特性は
以前に紹介しましたね。
ETFでは、
分配金の自動再投資が基本できないです。
分配金は現金で受け取るのが基本です。
というのも、
ETFは最低単元で購入するのが基本で、
株式と同じようなものです。
| 銘柄名 | 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100) |
| 最低購入単元 | 10株~ |
| 分配金 | 2024/7 128円/10口 2025/1 130円/10口 |
この場合で見ると、
10口持ってた場合、年間で258円です。
上記の銘柄の最低購入金額は50万470円です。

分配金では到底買えないですね。。
このように最低購入金額を
上回ることがならない場合、
基本購入できないです。
またいっぱい購入して、
最低購入金額を上回る場合でも、
基本的に口座に振り込まれます。
一旦、税金など引かれた形で
手元に入るので、
その分配金から
自分で同じETFを買わないといけない。
こうなると手数料等が引かれるので、
複利の力という恩恵が得られないです。
ただ株式同様に配当金目的ってことなら良いですね。
信用取引
詳しくは別の機会で紹介しますが、
簡単に説明すると、
自分の持ってないお金以上で
株式を売買できるようなものです。
信用取引は
ハイリスク・ハイリターンな手法なので、
初心者にはおススメできない取引です。
株式で使われる取引で、
ETFも株式同様の購入方式なので、
信用取引が可能となっております。
コストについて
管理費に関しては、
ETFの方が比較的に安く設定されてます。
ただ最近の投資信託は
かなり安いコストの商品もあります。
| ETF | 投資信託 | |
| 銘柄名 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
| 信託報酬 | 0.066% | 0.08140% |
このように
同じS&P500への投資商品でも
ETFの方がコストが安くなってますね。
売買手数料は主にネット証券ではどちらも
基本的にゼロな部分も多くなっており、
違いとしたら、
投資信託の方が手数料無料の銘柄が多いです。
為替手数料(海外ETFのメリット)
円→ドル、ドル→円の交換に
手数料が上乗せされることです。
投資信託では運用管理費に、
ETFでは
自身が売買時に負担するイメージです。
為替リスク
これはETFの特徴でもありますが、
ETFは上場してるということで、
海外市場に上場してれば
証券会社が海外市場の
購入可能地域なら
証券会社を通して
海外ETFも直接購入可能です。
基本的にアメリカ市場は
全世界から上場してる企業も多く、
他の市場で購入するより
購入しやすいのでおススメです。
アメリカ市場以外は、
証券会社によってはネットから購入
できない等の制限もあり
また投資信託は基本、
日本からの購入が基本なので、
直接購入ができない性質です。
例えば、S&P500を例にすると
バンガード・S&P500 ETF(VOO)
上記の米国ETFが有名です。
| 手数料 (経費率) | 0.03% |
| 価格 | 516.57USD ※2025/3/21 |
 | |
日本のS&P500の投資信託orETFより
かなり手数料が安く設定されておりますね。
VOOは様々なところの投資先にもなっており、
SBI・V・S&P500の商品もVOOを投資先として
S&P500を運営してます。
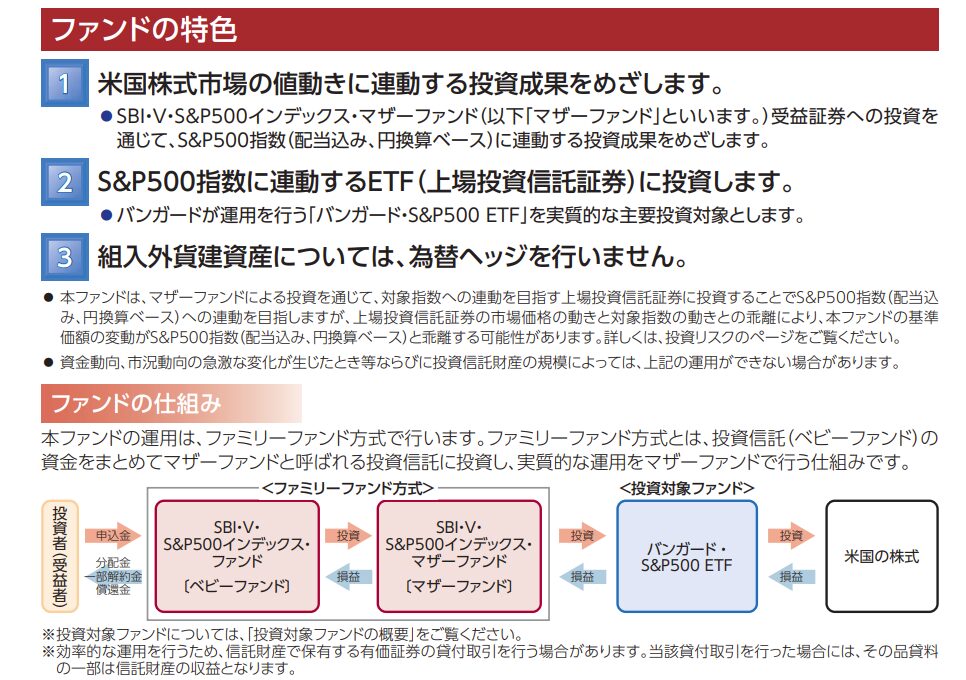
アメリカのS&P500に直接投資!
となった場合に人気なETFです。

値上がり率も大きい!!
日本から間接投資してる場合

S&P500上がったのにマイナス!?
日本からS&P500の
投資信託を買ってると
よく上記の現象があります。
これは円ベースで購入することで、
円安から円高になると、為替リスクからマイナスになることがあります。
1ドル=100円
米国株式(1株100ドル)を
100万円購入
1ドル=90円に
株価100ドル→110ドルに
11000ドル×90円=99万
1万円の損失
1ドル=110円に
株価100ドル→110ドルに
11000ドル×110円=121万
21万円の利益
このように円ドルの変化によって、
日本→外国の投資損益が発生します。
投資信託の価値からみると
為替リスクが起こりえる事象です。
アメリカ市場目的で購入してる商品の場合は、
円ベースで購入するより、
為替影響がない直接購入もETFでは可能です。
売却時も自身の判断でできるので為替リスクも回避できる
一方で為替での損益は管理しないといけません。
日本から購入する場合でも、
ETFの商品によっては
為替リスクを許容するかの有無が選べる商品があります。
「為替ヘッジあり」・「為替ヘッジなし」
この辺りはまた説明しますが、
為替での利益上下をさせるか、
させないようにするかの違いになります。
※投資信託は為替の影響が受けやすい商品がメインです
ETFの注意点・ポイント
ETFを選ぶ際にはいくつかの注意点があります。
まず、流動性の低いETFを選ぶと、
価格と評価の差が広がる可能性があるため、
注意が必要です。
購入する際は、
過去の取引量や
流動性を確認することが重要です。
流動性見るポイントです
- 流動性が多いと価格安定
- 手数料が安い
- 指数に連動する商品が安定
向いてる人・向いてない人
ETFは海外に強みもあるので、
直接購入で自身で管理したい人には
向いてる商品ではありますね。
ただ、損益がリアルタイムかつ
値動きも株価同様になるので、
投資信託よりリスクは大きいです。
NISAでの活用方法
NISAの詳しい説明は
別途記載しますが、
現在のNISAは簡単に以下の種類があります。
| 新NISA | ||
|---|---|---|
| 枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 非課税種類 | 売却利益、配当金 | |
| 期間 | ずっと無制限 | |
| 年間投資枠 | 120万 | 240万 |
| 非課税投資額 | 1800万 ※売却すると翌年移行再利用可 | |
| 内1200まで 使用可 | ||
新NISAは1800万までは、
運用益が非課税となる制度です。
ETFの活用方法は、
年間240万使える成長投資枠で
購入することがおススメです。
つみたて投資枠では
定額購入で投資信託を購入し、
その残り分は、成長投資枠で
自身の好きなテーマに沿った
ETFを購入するという手法が多いです。
非課税という枠はかなりメリットがあり、
まずは新NISA枠を埋めることが優先かな。
まとめ
メリット
デメリット
ETFはどういったものかを説明しましたが、
各商品でメリット・デメリットがあります。
ETFは少し上級者向けなので、
投資信託から始めるのがおススメです。
理論を理解し、自分に適した商品を選んで、
賢い投資を行いましょう。
次回以降は、
投資の入門について紹介しましたが、
応用編として
実際に投資する場合に関わることを
紹介させていただきます。